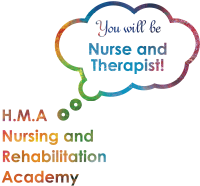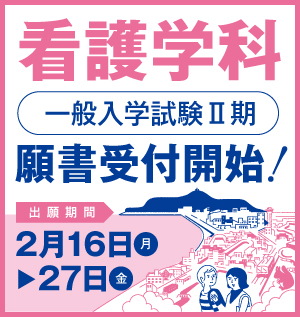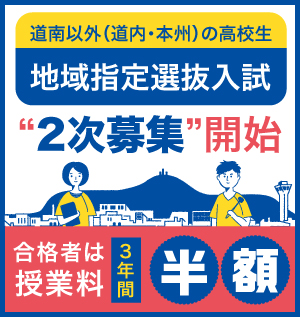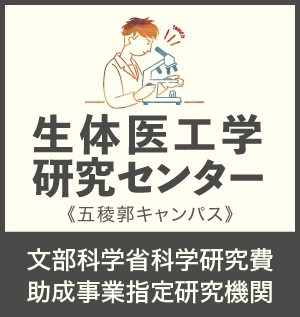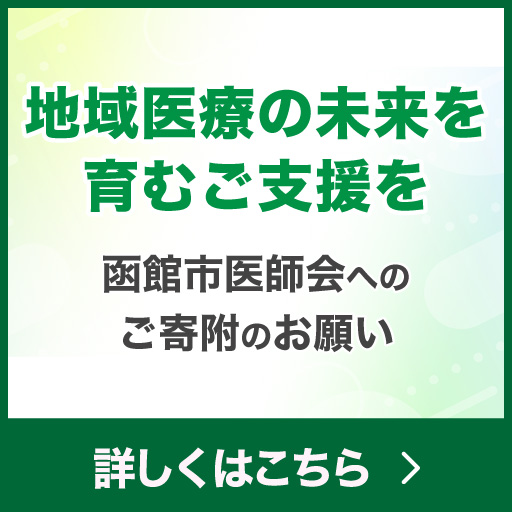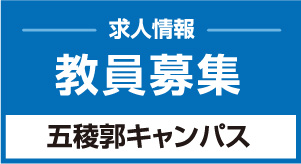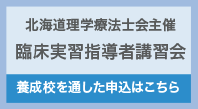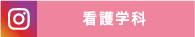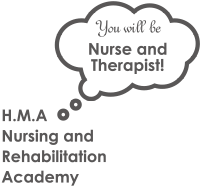生成系AIの使用方針
Policy for using generative AI
生成系AIの使用方針
Policy for using generative AI
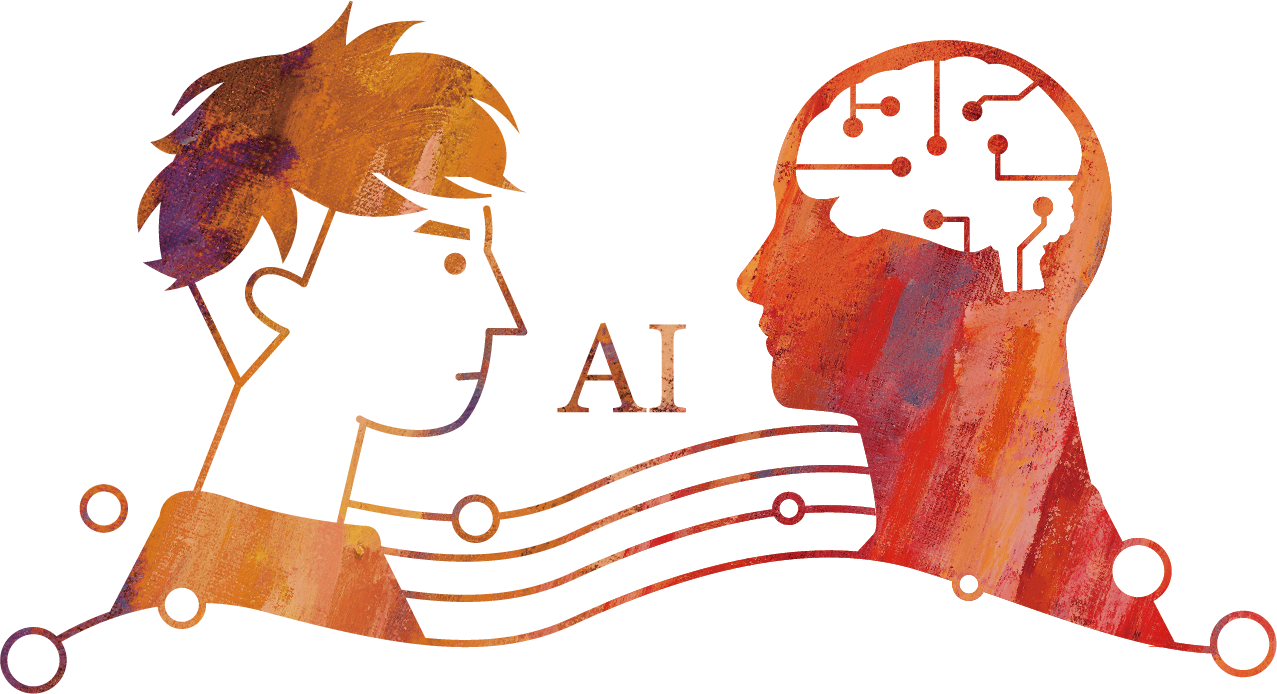
当学院における生成系AIの使用方針について
近年、生成系AIテクノロジーは急速に進化し、今後は私たちの生活に欠かせないツールとなりつつあります。医療ICTを推進する当学院では、Chat GPTなどの生成系AIを活用するには、著作権やプライバシーに関する法律を遵守するという倫理的な理解を高めることが重要です。
当学院の生成系AIの使用方針としては、生成系AIの仕組みや制約を理解し、日常生活での使用や講師が使用を許可した場合もしくは自己学習の際に自らの学びに相乗効果を期待できる建設的な活用については推奨します。しかし、臨床実習における使用は、個人情報保護の観点および症例を通して学生自ら考える機会を損なうデメリットの側面が大きいと考えています。また、実習等で知りえた対象者の個人情報を生成系AIに入力しレポート等を作成することは、実習施設における個人情報規定や当学院学則に抵触するため、一切の使用を禁止します。
今後何らかの機会で生成系AIを活用する際には、得られた結果を批判的に評価し、自分自身の意見を明らかにしながら分析を深めることが必要です。誤情報や誤解を避けるために、生成系AIの結果を慎重に評価し、リスク管理を徹底することも不可欠です。そのため、各教員が示すルールや指示を守り、生成系AIに関するリテラシーを高める姿勢が求められます。
※各項目クリックで詳細が表示されます
1.当学院における生成系AI使用時のルール
臨床実習での使用は一切禁じます。ただし、科目担当者や実習指導者により一部使用が許可となった場合は以下のルールを遵守してください。
- 1-1. 実習指導者や科目担当者から許可があり生成系AIを使用する場合は当学院が定めたルールや実習施設の規程および実習指導者に従うこと。実習地に規程や明確な見解がない場合は学院が定めたルールに従うこと。
- 1-2. 生成系AIの利用を認められた場合は自らが調べた引用表記、出典を必ず明示すること。
- 1-3. 生成系AIの出力結果(出典も含む)をそのまま提出物に切り貼りして用いる利用の仕方は禁じる。
- 1-4. 生成系AI・翻訳AIの出力結果に問題がないかを利用者が責任をもって確認すること。
- 1-5. 科目担当者からの許可があり使用する場合においても、個人情報に関する入力、特に実習時に知りえた症例の実名(入院施設や居住地域を含む)等を含んだ情報や評価結果を入力して文章作成することは固く禁じます。
- 1-6. 本ルールを破り、生成系AI入力において個人情報の使用が明らかになった場合は、当学院規程に照らし、懲戒処分対象となることがあります。
2.生成系AIに関連する法律と倫理の遵守について
- 2-1. 著作権とプライバシーの尊重
- 生成系AIが作成した内容が著作権法やプライバシー保護法に違反しないように注意することが重要です。引用や参考文献の明確な記載を心がけてください。
- 2-2. 適切な使用範囲
- 生成系AIの使用が学習目的に合致し、その利用が倫理的であることを確認しましょう。
- 2-3. 情報の評価
- 生成系AIから得られた情報をそのまま受け入れるのではなく、批判的思考を活用し、他の信頼できる情報源と照らし合わせて確認して誤情報を避けることが重要です。
- 2-4. 独自の視点の強化
- 生成系AIの結果を基に、自分自身の意見や分析を深めるための材料とし、単なる情報の羅列にとどまらないようにしましょう。
3.生成系AIをレポート作成や課題対応に使用するデメリット
- 3-1. 個人情報のリスク
- 生成系AIに個人情報を入力すると、情報が漏洩するリスクがあります。生成系AIは収集データ(各個人からの入力データなど)を学習に使用することがあるため、個人情報の入力が思わぬ形で拡散するリスクが予測されています。実習施設で知りえた個人情報を生成系AIに入力することは実習施設における個人情報取り扱い規程や当学院における学生心得など学則に係る各種定めに抵触します。
- 3-2. 誤情報のリスク
- 生成系AIの結果が必ずしも正確であるとは限りません。特に、新しい研究成果や最新の情報に関しては誤情報を含む可能性があります。そのため、生成系AIから得た情報は他の信頼できる情報源と照らし合わせて確認する必要があります。
- 3-3. 依存リスク
- 生成系AIに過度に依存すると、自分自身の思考力や問題解決能力が低下する可能性があります。生成系AIは情報収集やアイデアの補助として有用ですが、最終的な判断や分析は自分自身で行うべきです。
- 3-4. 倫理的な問題
- 生成系AIの使用には、著作権侵害やプライバシーの侵害といった倫理的な問題が伴うことがあります。
生成系AIが生成するコンテンツは必ずしもオリジナルではなく、他の作品を基にしている場合もあるため、適切な引用や著作権への配慮が必要です。 - 3-5. オリジナリティの欠如
- 生成系AIを使用して作成されたレポートや課題は、オリジナリティに欠ける可能性があります。自分の独自の視点や考えを反映させることが重要であり、生成系AIの結果をそのまま提出することは避けるべきです。
4.リスク管理の徹底
- 4-1. 誤情報の識別
- 生成系AIの結果を慎重に評価し、誤情報を識別する能力を養うことが不可欠です。
- 4-2. 個人情報の保護
- 生成系AIに個人情報を入力するリスクを理解し、必要な情報だけを扱うようにしましょう。
5.教員、臨床実習施設からの指導や規程の遵守
- 5-1. ルールと指示の遵守
- 生成系AIを用いる際には、教員から示される指示や実習地における規程やルールを守り、適切な範囲内で生成系AIを使用することが求められます。
- 5-2. リテラシーの向上
- 生成系AIに関する知識を深め、リテラシーを高めることで、より効果的にツールを活用できるようになります。
6.生成系AIが誤情報を提供してしまう理由
学習データの問題: 生成系AIは大量のデータを使って学習しますが、そのデータが完全に正確であるとは限りません。学習データに含まれる誤りやバイアスが原因で、AIが誤った情報を生成することがあります。
- 6-1. 解釈の誤り
- 生成系AIはデータを基に情報を生成しますが、その過程でデータの解釈を誤ることがあります。これは特に、曖昧な文脈や複雑な質問に対して発生しやすいです。
- 6-2. 推論の限界
- AIは与えられたデータから推論を行いますが、その推論が必ずしも正確であるとは限りません。特に、未知の状況や不完全な情報に基づいて推論を行う場合、結果が不正確になる可能性があります。
- 6-3. 更新の遅れ
- 現在の情報と比較して、学習データが古い場合、生成される情報が時代遅れとなることがあります。
- 6-4. 設定ミスやバグ
- AIシステムの設定やアルゴリズムに問題があると、誤った情報を生成することがあります。これには、プログラム上のバグや、予想外の動作を引き起こす設定ミスが含まれます。
これらの要因が組み合わさることで、生成系AIが誤った情報を提供することがあります。このため、生成系AIの情報を利用する際には、批判的な視点を持ち、他の信頼できる情報源(教科書や論文など)と比較することが重要です。
7.生成系AI使用のメリットとデメリット
メリット
- 情報収集の効率化
- 多様な表現の生成
- アイデア創出の支援
- 語彙力、表現力の向上
デメリット
- 情報の正確性、信頼性の確認が必要
- 原著性の確保が難しい
- 思考力の低下につながる可能性
- 著作権に関する問題
8.生成系AIを個人学習の促進を目的に用いる場合の注意点
- 8-1. 生成系AIの仕組みと制約の理解
- 生成系AIがどのように情報を生成するかなどその限界を理解しましょう。
- 8-2. 自身の生成系AI使用スキル向上と真摯に学ぶ姿勢
- 生成系AIを使用する際も、自身の知識やスキルの向上を常に意識し、基本的に学習は自分で問題解決するという真摯で学び続ける姿勢を持ちましょう。
9.生成系AIを正しく、効果的に活用するために
- 9-1. 生成系AIの仕組みを理解する
- 生成系AIがどのように文章を生成しているのかを理解することで、より適切な利用方法を身につけることができます。
- 9-2. 生成系AIの限界を認識する
- 生成系AIは万能ではありません。生成系AIの出力結果を鵜吞みにせず、自分で判断することが重要です。
- 9-3. 倫理的な観点から利用する
- プライバシー保護、著作権、フェイクニュースなど、倫理的な問題に配慮した利用が必要です。